2009年05月17日
アグーを考える ~「アグー」と「あぐ~」は違う?~
ジャスコ限定販売の報告はちょっと置いといて。
ここ1、2年くらいでしょうか?国際通りでやたらと「アグー」の看板が目立つようになりました。「アグーって幻の豚って言われてるのに、こんなにいるの?」なんて声もチラホラ。ウーム、、、
ちなみに僕が豚に関わっていると知ると、たいていの人が「アグー?」「アグー買えるの?」と聞いてきます。もちろん貴重な在来種を守りたいとは思っていますが、、、さすがに何度も訊かれると「アグー以外は豚じゃないのか!」といいたくなります(笑)
さておき。
今回はその「黒い豚・アグー」について、いつもお世話になっている大宜味の豚飼いこと山本大五郎さんが問題提起しておられるので、私の勉強メモついでにまとめてみます。間違いがあればお知らせください。ただし、かなり回りくどい文章ですので。
ここ1、2年くらいでしょうか?国際通りでやたらと「アグー」の看板が目立つようになりました。「アグーって幻の豚って言われてるのに、こんなにいるの?」なんて声もチラホラ。ウーム、、、
ちなみに僕が豚に関わっていると知ると、たいていの人が「アグー?」「アグー買えるの?」と聞いてきます。もちろん貴重な在来種を守りたいとは思っていますが、、、さすがに何度も訊かれると「アグー以外は豚じゃないのか!」といいたくなります(笑)
さておき。
今回はその「黒い豚・アグー」について、いつもお世話になっている大宜味の豚飼いこと山本大五郎さんが問題提起しておられるので、私の勉強メモついでにまとめてみます。間違いがあればお知らせください。ただし、かなり回りくどい文章ですので。
まずは先日、沖縄県内の新聞に掲載されたこんな記事から。

純血も交雑種も「アグー」 ブランド豚表記 明確な区別求める声
琉球新報2009.5.10
「あぐ〜」という商標を取り、「これがホンモノのアグーです!」と表示しているのが、JAおきなわブランド豚推進協議会さん。県内スーパーではよくこのマークをを見かけます。これは本来、大人気のアグーの偽物が出回らないようにするための手段です。
JAおきなわさんは商標を取る際、「あぐ〜」の定義をこう決めています。
『琉球在来豚「アグー」の血液(オス方)を50%以上有することで、「アグー」豚を交配して生産された豚肉を「あぐ〜」と呼びます。』
それがこちら↓

みんなで守ろう「あぐ〜」ブランド(JAおきなわ銘柄豚推進協議会)
沖縄県食肉センターHPより。クリックすると大きくなります。
つまり「半分アグーなら、あぐ〜と呼んでいいことにする」っていうルールを作ったんですね。
皆さんよくご存知のように、琉球在来種アグーと呼ばれる豚は、黒くてゴツっとしたあの人相が悪くて野性味あふれる豚さん。だけど、JAおきなわさんの生産している「あぐ〜」は、そうじゃないんです。実際に出荷しているのは、西洋種を掛け合わせた交雑種(アグー×LWなど)です。
簡単にいうと、「黒くない」んです。
私も実際には見たことないのですが、沖縄県食肉センターさんによれば「白に黒いマダラ模様の入ったのがほとんど」とのこと。交雑させた場合、黒毛は劣勢遺伝なので生まれてくる子豚はほとんど白くなっちゃうらしい。
ともかく、これは生産性を上げつつ肉質をよくするため畜産業ではごく当たり前に行われている交配法です。お店に並んでいるのはほとんどこういう2、3種類が掛け合わされた交配種の豚さんです。そのおかげで私たちは、美味しい豚肉を安く、安定して、いつでもどこでも買える訳です。
これが記事冒頭の疑問、「アグーって幻の豚って言われてるのに、こんなにいるの?」に対する答えのひとつです。アグーという名で呼ばれる沖縄の在来豚は、現在600頭、そのうち純粋種216頭とのこと(沖縄県畜産課、2007年)。これでは確かに幻です。ほとんどの人の口には入りません。
しかし、三元交雑種の「あぐ〜」の生産頭数は年間1万2000頭もあるわけです。(琉球新報2006.12.27)なるほどね〜。※ただし、1万2000頭でもまだ現在の流通量を満たしているとは思えない、つまり「偽物アグー」が出回っているのでは?と言われてしまっている訳です。ウーム、、、

商標「あぐ~」を販売している事業者
ところが、「半分でも『あぐー』って言っていい」ということになってしまうと、納得いかない方々がいる訳です。それは、真っ黒い、いわゆる純粋な「アグー」を出荷している養豚農家さん。せっかく苦労して生産性の低い豚(成長も遅く、子豚の数も少ない)を育てているので、付加価値を高めて(つまり高値で)売らないと採算が合いません。それなのに、半分だけの交配で効率よく「大量生産」したマダラの豚が「アグー」として流通してしまうと、消費者側には、「半分」なのか「純粋」なのか区別がつかない。
いちおうJAおきなわさんは『「あぐ〜」が市販されている銘柄肉(交配種)で、「アグー」が種としての豚の名前』と区別されているそうですが、ほとんどの消費者には「あぐー」と「アグー」の違いなんて理解していないと思います。
つまり、紛らわしい。
さらにひどいことに、たとえ「真っ黒」で「純粋」な豚であっても、JAおきなわさんと商標使用許諾契約を結ばないかぎり、「あぐ〜」という名称を使ってはいけないことになってしまった。もちろん「アグー」も「AGU」もダメ。「マダラな豚がアグー(あぐー)を名乗り、黒いアグーの方がアグーと名乗れない」という状況が生まれてしまっているわけです。
JAおきなわさんは「『あぐ〜』豚肉を生産販売する業者に門戸を開き、広く参加を求めています」としていますが、誇りと情熱を持って純粋種を育ててきた農家にすれば、「都合のいいルールを作っといて、アグーと名乗りたかったら契約を結べなんて、勝手なこと言うな!」という気にもなります。
そこで山本大五郎さんは「アグーを考える会」を立ち上げ、新聞紙上の論題や上記記事などのように問題提起してきました。
そして先日完成したパンフがこれです。↓
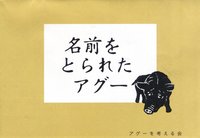

『名前をとられたアグー』(アグーを考える会)
「他の豚にアグーをかけあわせた交配種で、
沖縄のブランド豚を育てていくのはいいことだと思います。
でも、交配種や白豚を「あぐ〜」と言って売るとどうなるでしょう?
またひとつ「沖縄らしさ」を失ってしまう前に、
自分のモノサシをしっかりもって、考えてみてください」
ウチナーンチュとして、耳が痛い、というか心が痛い。ウーン、、、
僕は畜産振興を願う者として、JAおきなわさんの気持ちも分かる気がするのですが、消費者や市場が混乱する要因を放って置くのは、将来的にもよくないとは思います。アグーの定義を、もう一度みんなで議論すべきなのではないでしょうか。なんて結局、新聞みたいなまとめになってしまいました。
アグーを考える会・山本大五郎さんのHP「青空放牧豚」
最後に。
ブランド銘柄肉の大先輩、「黒豚」の定義はどうなっているかというと、
『黒豚』と表示できるのは、純粋種のみです。
※農林水産消費安全技術センター「食のQ&A、黒豚と表示できるのは」
※10年前にこんな議論や検討会を経て定められたそうです。↓
中央畜産会畜産情報ネット、月報「畜産の情報」(国内編)1999年7月
※最近はさらに「国産であること」という条件も含めるか検討されてます。(農水省畜産局による市場アンケート)
おまけ1:『みんなで守ろう「あぐ〜」ブランド』の詳細
***********************************
「あぐ〜」豚肉
食用豚肉としてひらがなで表記される「あぐ〜」の定義は、琉球在来豚「アグー」の血液(オス方)を50%以上有することで、「アグー」豚を交配して生産された豚肉を「あぐ〜」と呼びます。一般的な豚肉と比べて、さっぱりとした脂肪の旨味やまろやかな食感で人気の豚肉です。
「あぐ〜」商標について
JAおきなわは、旧沖縄県経済連時代の平成8年12月に「あぐ〜」の商標権を取得し(商標登録番号3231695号)、「あぐ〜」をJAおきなわ銘柄豚推進協議会が策定した品質基準を満たした高級の県産豚肉の統一ブランド名として使用しております。そして「あぐ〜」の商標については、JAおきなわと商標使用許諾契約を締結した事業者のみに使用を認めており、現在右に掲載されているシールを使用する5事業者と契約を締結してその使用を認証しています。よって、右のシールが貼付されている豚肉やその5事業者から「あぐ〜」豚肉であることの証明書の甲府を受けている業者が提供する「あぐ〜」豚肉は、適正に認められたルールの下で生産・販売されている安全・安心で美味しい「あぐ〜」豚肉です。JAおきなわが使用を認証していない業者が、「あぐ〜」、「アグー」「AGU」もしくその他の類似する名称を用いて豚肉を販売することは、このJAおきなわの商標権に違反するものです。
JAおきなわ銘柄豚推進協議会
「JAおきなわ銘柄豚推進協議会」は県内外の消費者に対して、安全・安心な沖縄ブランド豚肉「あぐ〜」を提供するため、豚肉の生産者や販売者が、適正に定められた一定のルールの下で、品質の高い「あぐ〜」の生産・販売をするようブランドを管理する組織であり、このルールに従って「あぐ〜」豚肉を生産販売する業者に門戸を開き、広く参加を求めています。
沖縄ブランド豚肉「あぐ〜」は、沖縄県の大事なブランドです。この大切なブランドを守り育てていきたいと思いますので、県民・消費者の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
お問い合わせ JAおきなわ銘柄豚推進協議会 JAおきなわ農業事業本部畜産部
***********************************
おまけ2:現在、商標使用許諾契約を締結している5事業者
(株)沖縄県食肉センター、(有)我那覇畜産※3銘柄、(株)那覇ミート※2銘柄、沖縄畜産工業(株)、(株)がんじゅう
おまけ3:アグー関連報道リンク
沖縄在来豚アグー 九州沖縄農業研究センター 2004年6月
http://www.knaes.affrc.go.jp/okinawa/letter/topic3/sub2topic3.html
琉球在来豚を守れ! アグー保存会設立 琉球新報2001.1.31
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-107272-storytopic-86.html
月刊養豚情報 2005年12月
http://www.keiran-niku.co.jp/youton-br0501.html
原種豚アグー5頭誕生
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-20017-storytopic-4.html
琉球大学がアグー精子の凍結保存技術を確率
http://www.u-ryukyu.ac.jp/univ_info/kouhou/newsletter/newsletter4/04.html
凍結精子でアグー誕生 琉球新報2007.4.24
http://web2.ryukyushimpo.jp/news/storyid-23238-storytopic-1.html
今帰仁アグーブランド化
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/noshoko/ninteijigyo/okinawa_yugafu.html
アグー販売店に認証制度 沖縄タイムス
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2008-09-13-M_1-009-1_002.html
アグー農家認証へ 琉球新報
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-135924-storytopic-4.html
幻の沖縄豚「アグー」が人気 「偽物多い」指摘も 朝日新聞
http://www.asahi.com/food/news/SEB200808160011.html
県アグーブランド豚推進協議会設立 沖縄タイムス
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2008-09-25-M_1-009-1_005.html
アグー純粋種守る 沖縄タイムス2009.2.11
http://www.okinawatimes.co.jp/spe/41vision/41vision_2009-02-11.html

純血も交雑種も「アグー」 ブランド豚表記 明確な区別求める声
琉球新報2009.5.10
「あぐ〜」という商標を取り、「これがホンモノのアグーです!」と表示しているのが、JAおきなわブランド豚推進協議会さん。県内スーパーではよくこのマークをを見かけます。これは本来、大人気のアグーの偽物が出回らないようにするための手段です。
JAおきなわさんは商標を取る際、「あぐ〜」の定義をこう決めています。
『琉球在来豚「アグー」の血液(オス方)を50%以上有することで、「アグー」豚を交配して生産された豚肉を「あぐ〜」と呼びます。』
それがこちら↓

みんなで守ろう「あぐ〜」ブランド(JAおきなわ銘柄豚推進協議会)
沖縄県食肉センターHPより。クリックすると大きくなります。
つまり「半分アグーなら、あぐ〜と呼んでいいことにする」っていうルールを作ったんですね。
皆さんよくご存知のように、琉球在来種アグーと呼ばれる豚は、黒くてゴツっとしたあの人相が悪くて野性味あふれる豚さん。だけど、JAおきなわさんの生産している「あぐ〜」は、そうじゃないんです。実際に出荷しているのは、西洋種を掛け合わせた交雑種(アグー×LWなど)です。
簡単にいうと、「黒くない」んです。
私も実際には見たことないのですが、沖縄県食肉センターさんによれば「白に黒いマダラ模様の入ったのがほとんど」とのこと。交雑させた場合、黒毛は劣勢遺伝なので生まれてくる子豚はほとんど白くなっちゃうらしい。
ともかく、これは生産性を上げつつ肉質をよくするため畜産業ではごく当たり前に行われている交配法です。お店に並んでいるのはほとんどこういう2、3種類が掛け合わされた交配種の豚さんです。そのおかげで私たちは、美味しい豚肉を安く、安定して、いつでもどこでも買える訳です。
これが記事冒頭の疑問、「アグーって幻の豚って言われてるのに、こんなにいるの?」に対する答えのひとつです。アグーという名で呼ばれる沖縄の在来豚は、現在600頭、そのうち純粋種216頭とのこと(沖縄県畜産課、2007年)。これでは確かに幻です。ほとんどの人の口には入りません。
しかし、三元交雑種の「あぐ〜」の生産頭数は年間1万2000頭もあるわけです。(琉球新報2006.12.27)なるほどね〜。※ただし、1万2000頭でもまだ現在の流通量を満たしているとは思えない、つまり「偽物アグー」が出回っているのでは?と言われてしまっている訳です。ウーム、、、

商標「あぐ~」を販売している事業者
ところが、「半分でも『あぐー』って言っていい」ということになってしまうと、納得いかない方々がいる訳です。それは、真っ黒い、いわゆる純粋な「アグー」を出荷している養豚農家さん。せっかく苦労して生産性の低い豚(成長も遅く、子豚の数も少ない)を育てているので、付加価値を高めて(つまり高値で)売らないと採算が合いません。それなのに、半分だけの交配で効率よく「大量生産」したマダラの豚が「アグー」として流通してしまうと、消費者側には、「半分」なのか「純粋」なのか区別がつかない。
いちおうJAおきなわさんは『「あぐ〜」が市販されている銘柄肉(交配種)で、「アグー」が種としての豚の名前』と区別されているそうですが、ほとんどの消費者には「あぐー」と「アグー」の違いなんて理解していないと思います。
つまり、紛らわしい。
さらにひどいことに、たとえ「真っ黒」で「純粋」な豚であっても、JAおきなわさんと商標使用許諾契約を結ばないかぎり、「あぐ〜」という名称を使ってはいけないことになってしまった。もちろん「アグー」も「AGU」もダメ。「マダラな豚がアグー(あぐー)を名乗り、黒いアグーの方がアグーと名乗れない」という状況が生まれてしまっているわけです。
JAおきなわさんは「『あぐ〜』豚肉を生産販売する業者に門戸を開き、広く参加を求めています」としていますが、誇りと情熱を持って純粋種を育ててきた農家にすれば、「都合のいいルールを作っといて、アグーと名乗りたかったら契約を結べなんて、勝手なこと言うな!」という気にもなります。
そこで山本大五郎さんは「アグーを考える会」を立ち上げ、新聞紙上の論題や上記記事などのように問題提起してきました。
そして先日完成したパンフがこれです。↓
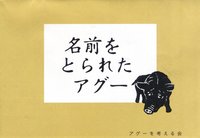

『名前をとられたアグー』(アグーを考える会)
「他の豚にアグーをかけあわせた交配種で、
沖縄のブランド豚を育てていくのはいいことだと思います。
でも、交配種や白豚を「あぐ〜」と言って売るとどうなるでしょう?
またひとつ「沖縄らしさ」を失ってしまう前に、
自分のモノサシをしっかりもって、考えてみてください」
ウチナーンチュとして、耳が痛い、というか心が痛い。ウーン、、、
僕は畜産振興を願う者として、JAおきなわさんの気持ちも分かる気がするのですが、消費者や市場が混乱する要因を放って置くのは、将来的にもよくないとは思います。アグーの定義を、もう一度みんなで議論すべきなのではないでしょうか。なんて結局、新聞みたいなまとめになってしまいました。
アグーを考える会・山本大五郎さんのHP「青空放牧豚」
最後に。
ブランド銘柄肉の大先輩、「黒豚」の定義はどうなっているかというと、
『黒豚』と表示できるのは、純粋種のみです。
※農林水産消費安全技術センター「食のQ&A、黒豚と表示できるのは」
※10年前にこんな議論や検討会を経て定められたそうです。↓
中央畜産会畜産情報ネット、月報「畜産の情報」(国内編)1999年7月
※最近はさらに「国産であること」という条件も含めるか検討されてます。(農水省畜産局による市場アンケート)
おまけ1:『みんなで守ろう「あぐ〜」ブランド』の詳細
***********************************
「あぐ〜」豚肉
食用豚肉としてひらがなで表記される「あぐ〜」の定義は、琉球在来豚「アグー」の血液(オス方)を50%以上有することで、「アグー」豚を交配して生産された豚肉を「あぐ〜」と呼びます。一般的な豚肉と比べて、さっぱりとした脂肪の旨味やまろやかな食感で人気の豚肉です。
「あぐ〜」商標について
JAおきなわは、旧沖縄県経済連時代の平成8年12月に「あぐ〜」の商標権を取得し(商標登録番号3231695号)、「あぐ〜」をJAおきなわ銘柄豚推進協議会が策定した品質基準を満たした高級の県産豚肉の統一ブランド名として使用しております。そして「あぐ〜」の商標については、JAおきなわと商標使用許諾契約を締結した事業者のみに使用を認めており、現在右に掲載されているシールを使用する5事業者と契約を締結してその使用を認証しています。よって、右のシールが貼付されている豚肉やその5事業者から「あぐ〜」豚肉であることの証明書の甲府を受けている業者が提供する「あぐ〜」豚肉は、適正に認められたルールの下で生産・販売されている安全・安心で美味しい「あぐ〜」豚肉です。JAおきなわが使用を認証していない業者が、「あぐ〜」、「アグー」「AGU」もしくその他の類似する名称を用いて豚肉を販売することは、このJAおきなわの商標権に違反するものです。
JAおきなわ銘柄豚推進協議会
「JAおきなわ銘柄豚推進協議会」は県内外の消費者に対して、安全・安心な沖縄ブランド豚肉「あぐ〜」を提供するため、豚肉の生産者や販売者が、適正に定められた一定のルールの下で、品質の高い「あぐ〜」の生産・販売をするようブランドを管理する組織であり、このルールに従って「あぐ〜」豚肉を生産販売する業者に門戸を開き、広く参加を求めています。
沖縄ブランド豚肉「あぐ〜」は、沖縄県の大事なブランドです。この大切なブランドを守り育てていきたいと思いますので、県民・消費者の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
お問い合わせ JAおきなわ銘柄豚推進協議会 JAおきなわ農業事業本部畜産部
***********************************
おまけ2:現在、商標使用許諾契約を締結している5事業者
(株)沖縄県食肉センター、(有)我那覇畜産※3銘柄、(株)那覇ミート※2銘柄、沖縄畜産工業(株)、(株)がんじゅう
おまけ3:アグー関連報道リンク
沖縄在来豚アグー 九州沖縄農業研究センター 2004年6月
http://www.knaes.affrc.go.jp/okinawa/letter/topic3/sub2topic3.html
琉球在来豚を守れ! アグー保存会設立 琉球新報2001.1.31
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-107272-storytopic-86.html
月刊養豚情報 2005年12月
http://www.keiran-niku.co.jp/youton-br0501.html
原種豚アグー5頭誕生
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-20017-storytopic-4.html
琉球大学がアグー精子の凍結保存技術を確率
http://www.u-ryukyu.ac.jp/univ_info/kouhou/newsletter/newsletter4/04.html
凍結精子でアグー誕生 琉球新報2007.4.24
http://web2.ryukyushimpo.jp/news/storyid-23238-storytopic-1.html
今帰仁アグーブランド化
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/noshoko/ninteijigyo/okinawa_yugafu.html
アグー販売店に認証制度 沖縄タイムス
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2008-09-13-M_1-009-1_002.html
アグー農家認証へ 琉球新報
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-135924-storytopic-4.html
幻の沖縄豚「アグー」が人気 「偽物多い」指摘も 朝日新聞
http://www.asahi.com/food/news/SEB200808160011.html
県アグーブランド豚推進協議会設立 沖縄タイムス
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2008-09-25-M_1-009-1_005.html
アグー純粋種守る 沖縄タイムス2009.2.11
http://www.okinawatimes.co.jp/spe/41vision/41vision_2009-02-11.html
Posted by mkat at 01:00│Comments(2)
│豚をめぐるあれこれ
この記事へのコメント
まきしさま、こんばんは。アグーでごはんの盛り上げ役ちんどん、ありがとう!!
こんなに丁寧に、わかりやすく、書いてくれてありがとう。ずいぶん時間もかかったことでしょう。書くこといっぱいあるだのに、ありがとう!!こうやってみんなが伝えてくれるので5月25日の琉球新報論では弁理士の方からのJAおきなわへの質問状がのってます。
僕もまきしさんと同じように沖縄の畜産振興を願い微力ながら尽力しています。でもこの[あぐ~」関係者の考えは、絶対にマイナスでしかないと僕は考えます。これからもどんどんこのことは伝えていきます。よろしくおねがいします。
こんなに丁寧に、わかりやすく、書いてくれてありがとう。ずいぶん時間もかかったことでしょう。書くこといっぱいあるだのに、ありがとう!!こうやってみんなが伝えてくれるので5月25日の琉球新報論では弁理士の方からのJAおきなわへの質問状がのってます。
僕もまきしさんと同じように沖縄の畜産振興を願い微力ながら尽力しています。でもこの[あぐ~」関係者の考えは、絶対にマイナスでしかないと僕は考えます。これからもどんどんこのことは伝えていきます。よろしくおねがいします。
Posted by やまもと at 2009年05月28日 22:10
私の勉強メモのようなものなので、まだまだピント外れのような気がして恥ずかしいですが、、、。
25日の新聞、またまた見逃していました。明日読んでみます〜
25日の新聞、またまた見逃していました。明日読んでみます〜
Posted by マキシ at 2009年05月28日 22:36
at 2009年05月28日 22:36
 at 2009年05月28日 22:36
at 2009年05月28日 22:36














